「摘果作業」正直、苦手です。毎年、気候も樹の状態も異なります。

昨年こうだったから、今年もこうしよう
とはならないのです。毎年毎年園主に聞くので
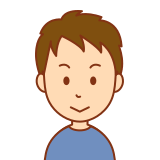
え~?今更?
と独り言のように言われてしまいました😢私もそう思います。でも、摘果は樹を弱らせてしまうし我が家の経済状況に直結するので、ついつい慎重になってしまいます。
摘果の仕方
摘果は自然落下が終わるころから始めます。実の付き方、品種等により摘果の仕方や時期は異なります。また、摘果は「粗摘果」と「仕上げ摘果」の2段階があり、着果量が多い樹を早い時期に摘果するのが「粗摘果」、最終的に数や大きさを調整するのが「仕上げ摘果」です。
当園で栽培している温州ミカンは7月~8月中旬ころにかけて粗摘果を行います。過剰な着果は、ジベレリンというホルモン成分が枝に蓄積され、翌年の開花が抑制されるため、なるべく早い摘果が重要です。
果樹のふところやすそ部分を落とし、混み合っている部分の間引き摘果を行います。
ここで心がけているのが、果実1個あたりの葉が、25枚前後になるようにすること。また、枝の先のミカンを残すことです。
木からの水分が少なく栄養が凝縮されているため、細い枝の先端のミカンは濃厚で甘みが強くなる傾向があります。
8月下旬~9月にかけて仕上げ摘果を行います。
表皮に傷が付いた果実や変形した果実、日焼けして黄色く硬くなった果実などを落とします。また。最終的に間引き摘果をして数の調整をします。この仕上げ摘果によって、収穫時の手間や選果の労力を軽減することが出来ます。
現在の当園の摘果状況
当園は主に早生ミカンの田口早生と宮川早生、中生ミカンの南柑20号を栽培しています。
昨年の当園の収穫量は、温暖化、干ばつ、カメムシ被害等で例年の3分の1しかありませんでした。その影響で隔年結果となり、今年の収穫量は例年より多い見込みで、摘果に励んでいますが・・・

分からなくなった…着果が多いのに、ミカンはこの時期にしたら大きい…摘果したいけど摘果してミカンが大きくなりすぎたら困るし、かと言って摘果しなかったら来年着果しなかっても困る…😿
実は私、一昨年の摘果に失敗してしまいました。一昨年、大きさが良いからと軽めの摘果にしました。一昨年の収穫時は良かったのですが、昨年着果量が激減してしまったのです。これまで何度も申し上げている気候の影響にプラスして一昨年の摘果の失敗が影響してしまいました。
当園は樹齢が経った園地を毎年改植しています。なので、どの園地も比較的若い樹が多いんです。ミカンの木も人間同様、若い木は元気があるため比較的毎年実を付けてくれます。その若木たちが昨年はあまり実を付けてくれなかったのです。
その結果、今年は着果量が多いうえに実も大きい…今年の若木の早生の園地の摘果は、変形果を作らないよう最小限の間引きだけすることにしました。
一昨年の摘果に多少責任を感じています。どうか来年も着果してくれますように!
摘果ミカンシロップ
先日作ったミカンシロップのその後です。(参照:摘果作業の目的と摘果ミカンの活用法)


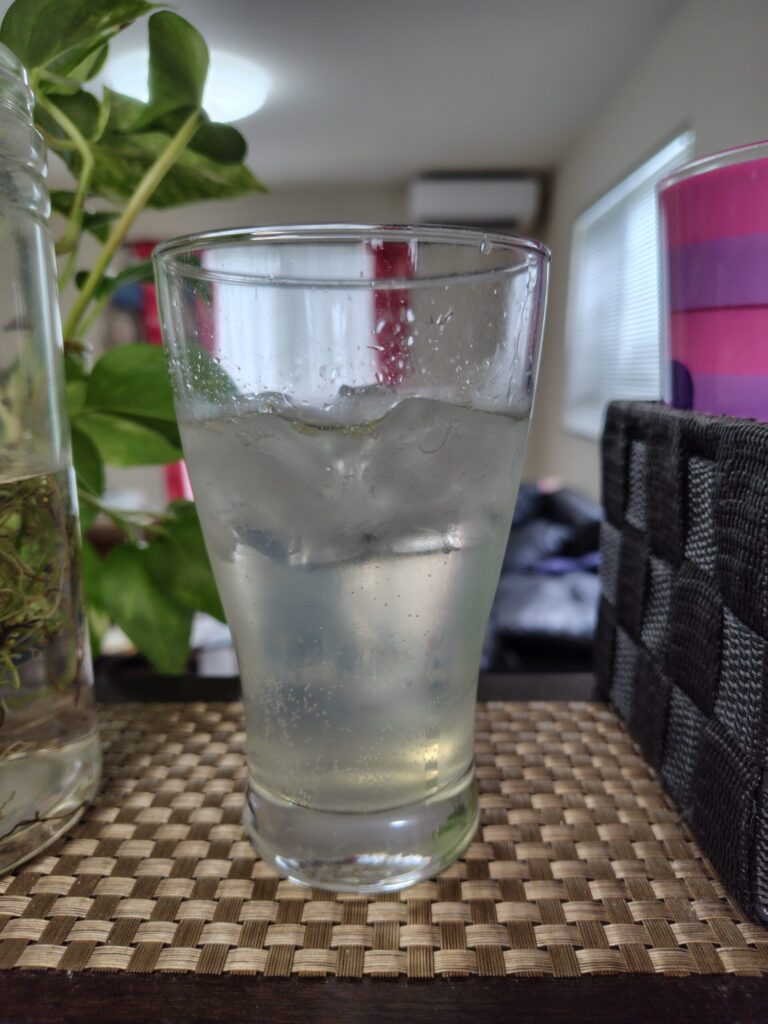
結 果…
果実の色が変わった。レモンだと皮が厚く硬いからか変化が無かったのに、摘果ミカンだと色が悪くなり食欲をそそらない。
逆にシロップ自体はレモンが無色に近かったのに対し、きれいな色をしている。
炭酸水で割って飲んでみた。
正直、少し青臭さがあり、好みもあるが好んで飲もうとは…レモンは炭酸水で割ってレモンジュースにしたりホットレモンやレモンティーにして飲んだりするが、この摘果ミカンシロップは飲むよりかき氷のシロップにする方が合っているように思う。

まだまだ研究が必要なようです。
まとめ
ただちぎるだけ。と思われがちな摘果作業ですが、この作業によってミカンの樹の成長もミカンの品質も我が家の経済も変わってくる重要な作業が摘果です。
気候、着果量、品質、樹の樹齢などによって方法が異なる作業。私はあまり得意な作業ではありませんが、勉強と経験を積んで美味しいミカンを栽培できるように努力します。




コメント